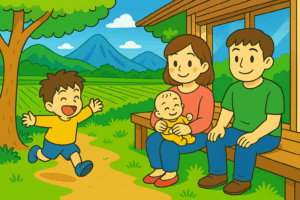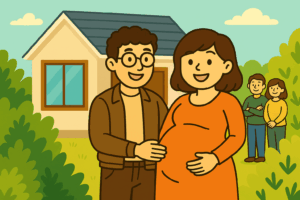2025/4/18・19小鹿野町の春祭りが開催された。
大勢の大人たちが、巨大な屋台を押していた。身体をめいっぱい使いながら、
息を合わせて、声を重ねて、全身で前へ進んでいく。
その光景に、最初の一歩で心をつかまれた気がした。
人の熱量。地域の一体感。そこにあったのは、理屈じゃない。もっと原始的で、むき出しのエネルギーだった。
「人って、こんなふうに一緒になれるんだ」——そう感じさせる場面だった。
今年、はじめて小鹿野町の春祭りを訪れた私は、まだこの町の“よそ者”だと感じていた。
町の“素顔”に出会う日
華やかな衣装を着て歩く少女たち。屋台の下で汗だくになりながら大きな声を出す男たち。
屋台の周りには「わっしょい!」と大きな声が響く。
写真では何度も見たことのある風景だった。
でも実際にその場に立ち、音や声、地面の振動を身体で感じてみると、
写真で見るそれとはまったく違うものだった。




祭りのものすごい熱量の空気に圧倒されながら少しずつ歩いた道には、春の陽ざしが容赦なく照りつけていた。
4月なのにまるで夏のように暑い。
思った以上に体力も使ったが、それさえもこの祭りの“熱”の一部だった気がする。
普段は役場の同じフロアで顔を合わせている職員さんたちも、この日は法被をまとい、それぞれの持ち場で祭りを支えていた。
いつもとは違う、覚悟のにじむ表情と、ときおり見せる笑顔。
真剣に動く姿には、町の祭りを支える一人ひとりとしての、誇りと責任がにじんでいた。
そんな中、ふとこちらに気づいて声をかけてくれたのは、町内に住む女性だった。
仲間たちと心からの笑顔をカメラに見せてくれた。
他にも、同じ小学校やこども園に通う子どもを持つママ友や、役場の職員さん、
仕事上の関わりのある人たちと、何人もすれ違った。
立ち止まって、たわいのない会話を交わす——そんなひとときも、祭りの中に自然に溶け込んでいた。
知っている顔にたくさん会えること。
それも、この町で暮らしながら迎える祭りの楽しさなのかもしれない。


思いがけない再会と、嬉しいシャッター音
人混みの中、以前協力隊として活動していた先輩の姿を見つけた。
法被をまとい、祭りの中でも重要な役割を担っている様子だったのに、
ふと目が合うと「あぁ!松田さん。撮ろうか?」と気さくに声をかけてくれて、
息子と一緒の写真を何枚も残してくれた。

その自然な優しさと、頼もしさのギャップがなんだか嬉しかった。
ふだんは撮る側ばかりの私が、こうして“撮られる側”になったのは久しぶりで、気持ちがふっとほどけた。
仕事や立場を越えて、人と人とがまっすぐに関われる場。
祭りの中では、そんな関係性が日常の延長として自然にあらわれていた。
子どもは、もうこの町の一員だった
笠鉾の列が通りすぎようとしたとき、こども園時代のママ友が声をかけてくれた。
「もしだったら、引いてみる?」と、息子を誘ってくれたのだ。
その言葉を本人に届けないうちに、息子は何のためらいもなく、
すっと列に入り、自然な足取りでロープを引いていた。

私だったら、きっと遠慮してしまっていたと思う。
でも彼は、私がちょっと目を離しているうちにもう列の中に入っていたのだ。
正直少し驚いた。でも、無垢な存在の方が、こういう場所には自然と溶け込めるんだなと思った。
移住してきて日が浅い自分にとって、「お祭り」みたいな地域の深い行事は、
どこか自分とは距離のあるものに感じていた。
“見ている側”と“やっている側”の間には、目に見えない境界がある気がして。
でもこの日、誰かに声をかけてもらい、子どもが列の中に入っていく姿を見て、
「いま私は、ほんの少しだけその境界の上に立っているのかもしれない」と思った。
小鹿野町に来て初めての春祭り。
この場所に来て歩いて周り、音を聞き、人と話し、空気を吸ったから得られた体感は
私にとってかけがえのないものになった。
小鹿野町の春祭りは、ただの「伝統行事」という形式ばったものではない。
暮らしと切り離された存在ではなく、人びとの日常の延長にあって、地域の熱そのものを感じさせてくれる場だった。
都市部では、効率や利便性が優先される毎日の中で、
身体を使って、目的や成果とは関係なく熱中するような時間は、
どこか置き去りにされがちだ。
でもこの祭りでは、そうした“理由や目的を超えた時間”に、
人びとが全力で関わっていた。
声を張り上げ、身体をぶつけ、空気を震わせながら——
今を生きる住民たちが、自分のエネルギーを命懸けで発散する場として、
この祭りはたしかに“生きて”いた。
こんな文化が今も続いていることが、すごい。
その熱を、暮らしのすぐそばで感じられることは、本当に貴重だと思った。
都市部で暮らしていたときには、味わったことのなかった感覚。
意味や効率を超えたところで、人と人が身体でつながる。
そんな場が、ここにはちゃんとある。
だからこそ、この町で暮らすことは、何か大切なものを育てていける可能性を秘めているのだと思う。
まだ私は分からないことばかりだが、これからの暮らしを通じて息子と共に少しずつでも体感していけるのだろう。
これからの暮らしが、ますます楽しみになった2日間だった。
写真・文章 松田遼(Instagram)
「小鹿野での暮らしをもっと知りたい」と思った方へ。
実際に来て、町の空気や人とのつながりを体感できる移住体験ツアーをご用意しています。
👉 移住体験ツアーはこちら