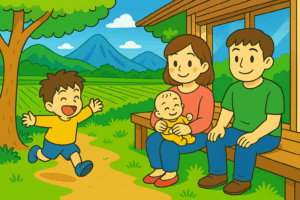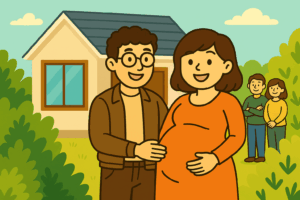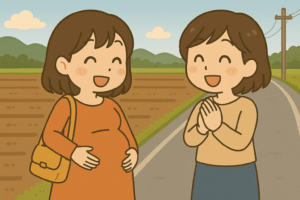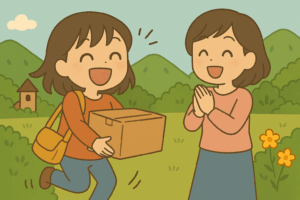埼玉県西部に位置する小鹿野町は、山あいに広がる地域で、平らな土地が限られていることから、農業には地形に合わせた工夫が求められます。
その中で、エゴマやカボスを育て、加工・販売までを一貫して行うことで、「持続可能な農業」を模索しているのが、
移住者の太田さんです。
栽培だけでなく、加工や販売までを自ら手がけることで、新たな農業の可能性を模索しています。
今回は、その取り組みや地域とのつながりについてお話を伺いました。

──改めて、太田さんはどんな農業をされていますか?
太田:エゴマを栽培して、加工・販売まで自分で行っています。
他には、カボスの果汁を仕入れて加工販売しています。いずれは自分でもカボスを育てたいと思っています。
農業の構造を見ていると、農家が儲からないのは「価格を自分で決められないから」だと感じています。
昔は、たとえばこんにゃくなんかも高く売れた時代がありました。
今は農協に出しても価格が決まってしまうし厳しい部分もありますが、その分、通販など自分で売る道も広がってきました。
今後もできるだけ自社で販売したいと考えています。
──小鹿野町で農業をするうえでの課題は?
太田:この地域は“条件不利地域”と呼ばれることもあって、山が近くて畑が斜面にあったり、まとまっていなかったりします。
他の地域では、100ヘクタール単位で畑があって大型の機械も入れるところもありますが、小鹿野は畑が小さいし道も狭いので、大きなトラクターも入りにくいです。
最初は、課題も正直よく分かっていませんでした(笑)でも、他の人がやっていたことを参考にしながら、
自分も少しずつ取り組んでいきました。
たとえば「しゃくしな」は生で売っても利益が出にくいけど、漬物にすることでしっかりと売れる商品になります。
エゴマも同じように、加工することで付加価値がつく。大変だけど、可能性はあると感じています。
これまでは「いい機械」と言えば大型機械でしたが、今はAIがタスクを出してくれたり、
水の管理をしてくれたり、小型トラクターでもGPSで動かせるようになっています。
今はまだ導入していませんが、こうしたツールを活用できれば、もっと可能性が広がると思っています。
──商品の魅力を教えてください
太田:無農薬・有機肥料で栽培していて、できるだけ地域内の資源を活用して作られているところです。
たとえばカボスの皮や米ぬかなど、地域の廃棄物を肥料として使って、持続可能な農業を目指しています。
外部資材に頼らず、自立できる農業が理想です。

食べ方としては炒りエゴマは料理にかけたり、おにぎりに混ぜたり、すり潰して和え物に使ったりできます。
味は控えめですが、プチプチした食感や香りが楽しめます。
油にすると量は減ってしまうけど、手軽に使える点では便利。栄養を重視する人には炒りエゴマの方がおすすめです。
あとは、カボスのポン酢も作っていて、豚しゃぶや牡蠣などによく合いますよ。
──地域の人との関わりは?
太田:農業を始めた頃、トラクターを借りたり、壊れたときに別の人からまた借りたり、思った以上に助けられてきました。
簡易ビニールハウスが風で倒れてしまったときも、すぐに声をかけてくれる人がいました。
畑を借りるにも、知らない人には貸しにくいですが、顔が見えてくると仕事も人間関係も広がっていきます。
最初から気にかけてくれる人がいて、「エゴマ仕入れるよ」と声をかけてもらったり、加工業者を紹介してもらったり。
商品を一人で配達するのは大変なので、委託して販路が広がるのはありがたいです。
困ったときに、必要な人を紹介してもらえる。そういうネットワークが、この町で生きていくうえではとても重要です。
この地域では畑も見られているので、ちゃんとやっているかどうかがすぐ伝わります。
噂も早いので、地道に信用を積み重ねることが大事です。

──これから農業を始めたい人へのメッセージをお願いします。
太田:まずは「やってみたらいい」と思います。ただその時に意識して欲しいのは、
作って終わりではなく、「どう売るか」までを考えないといけないということ。
特に小鹿野では、たくさん作ることで利益を出すのは難しいです。
畑だけでは農業は成り立ちません。道具や施設、関係づくりも含めて考える必要があります。
でも、農家というより「経営者・個人事業主」として取り組むつもりなら、きっと楽しいと思います!
太田さん、今回は改めてありがとうございました。
写真・文章 移住相談員 松田 遼
「小鹿野での暮らしをもっと知りたい」と思った方へ。
実際に来て、町の空気や人とのつながりを体感できる移住体験ツアーをご用意しています。
👉 移住体験ツアーはこちら