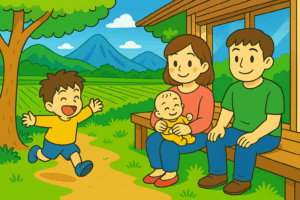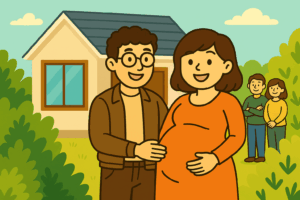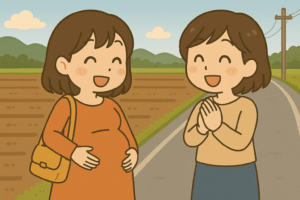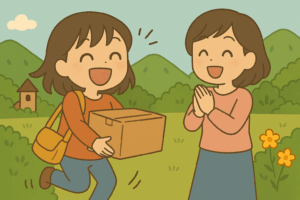二拠点生活と一言に言っても、さまざまなスタイルがある。夏には涼しく冬には暖かい地域に移動して過ごす暮らし方や、平日に仕事をしながら都心で過ごし、休日はのんびりと田舎暮らしを楽しむ生活など、人によって様々だ。
その中から、今回お話を聞いたのは、2024年12月から小鹿野町地域おこし協力隊として活動し、東京と小鹿野町の二拠点で「仕事」と「農業」の両立に挑戦している芦田央(あしだ・ひろし)さんだ。
二拠点生活を始めることになった経緯や、実際に始めてみて感じたこと、小鹿野町でこれから挑戦していきたいことなど、二拠点生活について気になることをうかがった。
二拠点生活の始まりは住民とのつながりだった

芦田さんは、どのようにして”小鹿野町”を知ったのですか?
「小鹿野町に憧れて来たというよりは、”呼ばれるようにして”たどり着いたのが小鹿野町だったという感じです。」
呼ばれるようにしてたどり着いたというのはどのような経緯で?
「小鹿野町に移住してきて、今では小鹿野町の住民となった女性(以下:師匠と呼ぶ)が、都心の人に向けて、農業体験をしてみませんか?と、呼びかけをしていたのです。それは事業としてではなく、仲間内のコミュニティー感覚で行われていました。そこに通っていた友達から、声をかけられ参加したのがきっかけでした。師匠は自然農法でやっている田んぼや畑の手伝いを、仲間同士の声掛けで輪を広げているのです。」
初めて参加したときの感想は?
「その日は、小雨の降る日の稲刈りでした。正直、お米づくりは大変だと感じました。田んぼの中はぬかるみ、機械を使用しない手刈りで、稲架掛け(はさかけ)も、自分たちの手で組み立てました。」
もともと家庭菜園が好きで、プランターで野菜を育てていたという芦田さん。この体験を通して、大変でもお米づくりへチャレンジしたい気持ちが強まったそうだ。
今年は自分でお米づくりに初チャレンジですか?
「そうですね。お米ができるまでには様々な工程があり、機械や設備のない素人だけではなかなか参入ハードルが高いのですが、師匠や地域住民の方が前向きに協力してくれることで、チャレンジしてみようと思いました。」
小鹿野町住民とのつながりがあるからこそ、チャレンジができるのですね
「お米を上手につくるには、冬から作業を開始しなければなりません。土に空気を含ませ、寒さで雑草の種が少しでもなくなるようトラクターで耕運し、春にも同じ作業を行います。4月になると用水路から水を引き入れられるようになるので、“くろ塗り”や“代掻き”と呼ばれる、田んぼの水が漏れないようにするための作業をして、並行しながら苗を育てて、6月ごろに田植えを行います。
そのあとも、除草作業をこまめにしなければなりません。手間のかかる作業を経て、10月〜11月に稲刈り。刈った稲は2週間ほど干し、脱穀と籾摺り(もみすり)をすればようやく新米ができるんです。
地域住民と、二拠点生活や移住者の橋渡しをしてくれる”農業の師匠”と出会えたことで輪が広がりました。二拠点生活をしている方や、移住者にとって地元で出会うキーパーソンは、とても大切な存在です。たくさんの人に助けられながらではありますが、今後も挑戦していこうと考えています。
それに加え、住民のお誘いや集まりには顔を出す。そうすることで、自分の顔や名前を知って貰えます。さらに新たな人とのつながりや、輪のなかに入りやすくなるのではと、考えています。」
小鹿野町で生まれ育った筆者にとっても、この考えは素晴らしいチャレンジであると考える。なぜなら、地方の住人は”知らない人”への警戒心が強いからだ。さらに横のつながりも強く、住んでいる場所、顔や名前を知って貰えるまでが大変なのだ。誘いや集まりに積極的に参加する。そこで顔や名前が分かると住民の警戒心は一気になくなり、輪の中へ入りやすくなる。また、”人なつっこさ”が可愛がられるポイントでもあるのだ。
二拠点生活!芦田流はハードスケジュール

実際に二拠点生活を始めてみてどうですか?
「想像していた以上に、今は厳しいですね(笑)。
協力隊になる前に想像していたのは、東京7割、小鹿野3割という配分の生活でした。実際に始めてみると、小鹿野町での生活が思っていた以上にハードだったため、小鹿野町の滞在時間を増やすスケジュールを組み立てた結果5:5で行き来することになった感じです。」
かなり厳しいですか?
「楽になるように調整はしているのですが、まだ手探り状態でどんな方法が効率的なのかを模索中です。東京と小鹿野町に1週間ずつくらい滞在するのが理想的なスケジュールなのですが、小鹿野での用事が、小鹿野に滞在する1週間に上手くはまらないケースがあり、それは東京の用事も同様で、実際には2泊や3泊で行き来するハードな日程になることがあります。」
二拠点生活で自分なりに工夫していることはありますか?
「工夫していることは、車での移動時間ですかね。東京の拠点は立川にあって、小鹿野からだと移動に2時間〜2時間半ほどかかります。ですが、夜10時過ぎに出発すると道が比較的空いているため、速いときには1時間40分ほどでスムーズに移動ができることに気づきました。」
東京での仕事と小鹿野町での仕事に加え、農業もしているからハードになってしまうんでしょうね。東京では、どのような仕事をされているのですか?
「東京での仕事は、映画ライターやマーケティング支援、SNSコンサルティングなど平均して5つくらいの仕事をしています。どの仕事をするかで生活スタイルは変わりますが、基本的に規則正しい生活を心がけています。」
映画ライターの仕事には、どのような業務があるのですか?
「公開前の映画を試写で観て「観たい」と思ってもらえるように記事を書いたり、国内外の映画祭に参加して取材を行い、記事にしたりしています。」
そのため移住ではなく、二拠点の生活スタイルを採用しているのですね。
「そうですね。映画を観て書く記事は、大画面で観ないと分からないことが多いです。映画会社の試写室に足を運んで関係者として映画を観ることや、映画監督や俳優さんへのインタビュー取材などもあるので、東京と小鹿野町の二拠点での活動を採用しました。」
次に小鹿野町でしている主な業務を教えていただけますか?
「小鹿野町に移住したい方や、二拠点での生活希望者を増やし、サポートをすることがメインのミッションです。具体的には、小鹿野町移住サイトの運営や、掲載する記事の執筆など移住プロモーションをしています。」
ほかにサポートしている業務はありますか?
「移住者向けに無料で貸し出している”お試し住宅”のチェックイン・アウトや、アテンドの業務も担当しています。移住希望者のしてみたい事柄に対して、それに合う住民の紹介やサポートも大切な仕事になります。役場の担当者と連携を取り、希望者に情報提供をすることも小鹿野町でしている仕事のひとつです。」
お試し住宅は、1泊から最長9日まで住むことが可能。二拠点生活や移住を検討している方は、ぜひ活用してほしい。
小鹿野町と都心部の橋渡しにチャレンジしたい

小鹿野町では、町と一般社団法人おかえり集学校、株式会社LIFULL(ライフル)の3社で女性のリモートワーク支援をおこなっている。協力隊として、この支援にも関わる芦田さんは次のように語っている。
「リモートワークを始めた方達に、私の東京での仕事を依頼していきたいと考えています。ライフルの研修を受けた方々に、リモートワークでもっと稼げるようになってほしいんです。」
芦田さんの視点から、都心部と地方での仕事の差はどのように感じていますか?
「正直に言うと、都心と小鹿野の給料水準には、かなりの差があると感じています。ただ、それが良い方向に働くこともあって、例えばLIFULL事業を卒業した女性ワーカーさんたちにとって良い額の報酬を用意しても、それが都市圏では「安い」と歓迎されることがあるんです。このようなお互いにとって良い関係で、仕事を続けていける導線を作れたらと考えています。
町の経済活動の一部として、東京の仕事を小鹿野町の人にお願いすることや、お願いできる人材を増やしていくことが、今後の目標です。」
経済の流れとして、都市圏の賃金が地方に流れてくれたらいいと考えているそうだ。
ほかにチャレンジしたいことがあれば教えていただけますか?
「小鹿野町にある耕作放棄地(こうさくほうきち)を何とかしていきたいですね。小鹿野町だけでなく、地方では人口の減少により畑や田んぼが、数多く放置されたままになっています。その一方で都市圏の畑レンタルサービスでは、数メートル四方の小さな畑を借りたい人が続出し、順番待ちをしているような状況です。」
それこそ二拠点生活や移住をして、農業を始めてほしいですね
「そうなんです。日本は水も自然も豊かなので、自分の畑や田んぼで、少しでも食料を自身でまかなうことができたら、日本が輸入に頼る量も減らせるのではないかと常に考えています。」
また、都市圏の人たちに”もっと土と触れ合って欲しい”という思いもあるという。農業をやる人手が居なく、困っている地方の人。農業をしたいけど土地がない都心部の人。そこを上手につなげる”橋渡し”をすることが、今後の課題だ。
「まだ正解は分かりませんが、ここで成功すれば、ほかの自治体にも横展開できるのではないかと考えています。」と目標に向かってイキイキと語る芦田さんの笑顔が印象的だった。
取材・執筆:田部井斗江
写真:松田遼
秩父郡小鹿野町(おがのまち)では、移住を検討されている方向けに、実際の生活を体験できる「おためし移住住宅」を提供しています。
リアルな暮らしを体験いただけるよう、町民とのコミュニケーションや農作業体験、鳥獣害対策の見学などのアクティビティも選択できるコーディネーター伴走型、2泊~最長9泊が可能で、利用料は無料(2025年9月現在)です。移住のご検討にあたっての情報収集として、ぜひお気軽にご利用ください。