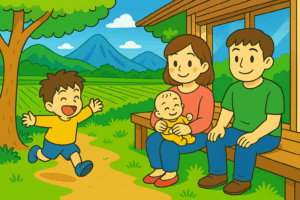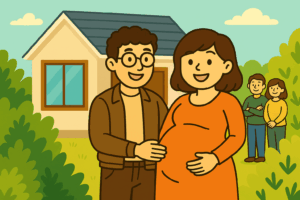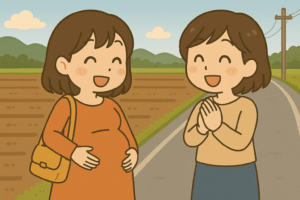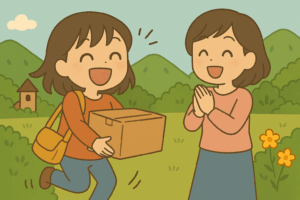年間を通じて、大小合わせて200以上のお祭りがある秩父郡の小鹿野町(おがのまち)。その多くは、開催される地区の町民が運営し支えている。エリアや祭の規模によっては、その年の運営担当地区が毎年交代。祭りの運営を担当する地区・人のことを、小鹿野では“行事”と呼んでおり、各地区の行事を束ねるのが“行事長”である。
小鹿野のお祭りの中でも、毎年12月に開催される「八幡神社例大祭(通称:鉄砲まつり)」は、一斉に発砲される火縄銃、そのなかを駆け抜ける2頭の御神馬、発砲が奉納行為となる珍しさなどを目当てに、多くの観光客が訪れる人気のお祭りだ。
そんな伝統ある「鉄砲まつり」が開催される下郷地区に、3年前、東京から夫婦2人で移住してきたKさん。「どういう50歳になりたいか」を念頭に人生設計し、移住に踏み切ったKさん夫妻は、「鉄砲まつり」の行事長を、移住後わずか1年で務めることに。分からないことも多いなか、お祭りに深くかかわったことで、地域に一気に溶け込み馴染むことができたと語っている。今回はKさんに、“行事長”としてお祭りに関わることになった経緯や、実際に携わってみての感想、移住者として気を付けたいマインドなどについて、幅広くお話をうかがった。

地域に支えられながら挑んだ、初めての「鉄砲まつり」で行事長
行事として関わる前から、「鉄砲まつり」とのつながりはあったんでしょうか?
実はそれまで、全くなかったんです。おととしくらいに、私たちの住む地区が「来年は親行事の担当だよ」って教えていただきまして。ウチは“和田”という地区なんですが、和田地区のなかで私たちが属する組では「移住してきた人は、まず地域のことを深く知るためにも行事をやってもらうのがいいのでは」という流れがあるんです。近所の方は「移住者が来ている」ということもすでに把握してくれていました。
それで、「鉄砲まつりの行事をやるなら、まず本番を見ておかないとやばいよね」と、おととし初めてお祭りを見に行きました。実際に見たら「本当に自分たちにできるのか…?」って思いましたね。
なのに、いきなり行事長を務めることになったんですね。
「行事長を決めよう」という話し合いの場があったんですけど、ご年配の大先輩やベテランの方もいらっしゃいますから、譲り合う形でなかなか決まらなかったんです。そこで膠着した議論を進める妥協案と言いますか、「まだ何も分からない新参者だから、“副行事長”的な役回りだったらやります」という提案をしたんです。それでも結局決まらず、「やり方は本当にわからない、皆さんで教えて支えてくださいね、私たちが一番お祭りのことを知らないからサポートしてくださいね」と念押しして、それで、“行事長”を自ら買って出ることになりました。
思い切った決断ですね。
私たちは新参者ですから、なかなか受け入れてもらえないのではないかという思いも、正直ありました。でも驚いたのは、みなさんとても協力的で本当によく動いてくれるんですよね。全部が終わったあと、「よくやり切れたね!行事長をやってくれてよかった」って言ってくれた方もいて。自分は突き進んでから考えるタイプなんですが、そういう関わりの中で地域の方とすごく打ち解け合えて、行事長をやってよかったと思います。

移住者として飛び込んだ地域の祭りー顔と名前を知ってもらうということ
実務としては、具体的にどのようなことを担当したんですか?
前提として、「鉄砲まつり」は神事なのです。神事の重要な部分は、八幡神社の宮司さんや、代々受け継いできた播磨家の方たちがまず第一にあって、その周りの部分を各エリアの行事が担当する、という体制なんです。
私の住む下郷エリアは和田地区で、その下郷の担当は笠鉾(かさぼこ)の花飾りの作成、前日の設置作業と人集め、当日の笠鉾の引き廻しなどでした。本番に至るまでの間にも、お祭りのエリア全体の調整や、役回りのある方の出演依頼もありましたね。「出演お願いできませんか?」と、1軒1軒お願いして回ったんです。本当はそこまでする必要はなかったらしいんですけど、私たちは勝手がわからないから、「回覧だけで済ませるのはよくないよね」って、足で回ったんです。そうしたら「あいつら頑張ってるな」というふうに見てくれて。
私は広告代理店でイベント業務も散々やってきているので、「催し物をやるということ」が、どういうことかは分かっているつもりです。だから今回も「これは祭りというイベントのディレクションだと思って取り組もう。だからまずは相手の顔を見に行こう。対面でのコミュニケーションを大切にしよう」と。
それでご挨拶がてら、とある地区に行ってみたら、会う人会う人が斎藤さん、浅見さん、栗原さんと同じ苗字の方が多くて、覚えるのに苦戦したという(笑)。
確かに、小鹿野町は同じ苗字の方が多い印象ですね。

全部で何軒くらい回られたんですか?
20軒くらいだったと思います。それぞれのエリアに行事がいまして、その行事たちを束ねるのが行事長という役割なので、行事の方に任せられるところはお任せました。
伝統あるお祭りを私たちが仕切っていることに、最初は「なぜ移住者が?」と思った方もいるかもしれません。しかし、行事長という役職に対しては少なくない敬意を持って接してくれるので、そこはありがたかったです。アドバイスをくださる方も多くて、やっぱり、みなさん「お祭りを成功させたい」という気持ちで声をかけてくれていたんですよね。町として、本当にお祭りを大切にしているんだなと実感しました。
お祭りで行事長を務めて、ご近所づきあいにも変化はありましたか?
祭りが終わったあとに、地元の方たちが「よくやったよ」みたいに声をかけてくれるんです。私たちをだれかに紹介するときには「移住してきたばかりなのに行事長を勤め上げた」と言ってくださったり。あるとき、地元のゴルフコンペがあって、参加したらお祭りで関わった方たちも来ていて、さらに仲良くなって、そのあとの飲み会までご一緒したり。
行事長として祭りに関わっていなかったら、そんなふうに話す機会もなかったと思うんです。やったおかげで一気に馴染めたというか、周囲の方も「私たちがどういう人か」を知ってくれたから、本当にやってよかったなって思いました。やっぱり顔と名前を知ってもらうって、一気に物事が進みますね。
「これには気を付けていた」という注意点はありますか?
「東京から来た人が偉そうにしている」という風に見えてしまうのだけは絶対にイヤでした。もちろん、そんなつもりは全く無かったですし。イベントのディレクション的な立場ですが、ちゃんと周りに聞いて、教えてもらいながら、言われたことをスルーせずに丁寧にやる。それだけは意識してました。こっちは教えていただく立場だし、移住者ですから。
伝統ある地域の大切なお祭りなので、「私たちが“新しい風を吹かせますよ」なんて言うのも違います。相手が大事にしているものを敬意をもって尊重する。お祭りに限らず、移住した方が一番に気をつけるべきところって、まさにそこだと思っています。

50歳を見据えた“暮らしの再設計”
そもそもなんですが、なぜ移住することになったんですか?
やっぱりコロナが大きかったですね。テレワークが増えて家にいる時間が長くなり、「DIYをしたい」という思いもあったので、空き家バンクでいろいろ探し始めました。そのときに小鹿野町の物件が出ていて、「見に行ってみたいな」と思ったのが最初のきっかけです。その頃の私たちは「小鹿野と秩父は大体同じ場所」くらいの認識でしたけど(笑)。
国際フォーラムでやっていた移住フェアにも足を運んで、移住相談員のお話を聞かせてもらって。小鹿野町には電車の駅がないということも、そのとき初めて知りました。
どういった経緯で、小鹿野町を移住先に選んだのでしょうか?
最初は、東京との往復で「どのくらいの移動距離が現実的か」でエリアを絞っていきました。千葉や神奈川は渋滞もあって、距離がネックになる。山梨も魅力的でしたけど、東京へ繋がる高速道路が中央道1本なので、これも混んだときが怖い。埼玉は正直、一番馴染みがなかったんですけど、「秩父あたりは水がきれいだ」というイメージもありましたし、秩父なら西武鉄道(特急ラビュー)を使えば、長野や静岡から新幹線で都心に出るよりも交通費がずっと安い。最後は、わりと勢いで決めちゃったところはありますね。
いつ頃から移住を検討し始めたのですか?
45歳ぐらいからでした。「どんな50歳になろうかな」と考えたときに、逆算してみたら「そろそろ何か動いてみない?」っていう時期で、ちょうど人生設計を考え直すタイミングだったんです。
生まれてからずっと東京に住んでいて、会社に勤めて20年くらい。六本木だ銀座だ赤坂だ、いろんな飲み屋に通っていたんですけど、朝まで飲んだら翌日は使い物にならない年齢になったし、そういうことにも飽きたし、もったいない時間の使い方をしているなって。「どんな50歳でいたいか」を改めて考えるようになったのは、そういう理由からです。
移住して3年目、そして50歳になった今、「“ウェルビーイング”な人生になっているな」と思っていて、決断してよかったと感じています。
どんなポイントで、そう思われたのでしょうか?
生まれてから50年、こういう自然が豊かな環境にいなかったので「知らないことがこんなに多いのか」って思うくらい、新しい情報ばかりで新鮮なんです。普段から食べてる野菜やお米が「作るの大変なんだろうな」って、なんとなくイメージはありましたけど、実際やってみたら想像以上に大変で。東京人にとっては、やったことないことだらけで全てが楽しい。田舎暮らしがしてみたいと思っても、事情があって都会を離れられない人もいます。ですが、思い切って決断と行動ができるかどうかで人生は変わると思うんです。
それとすごく感じているのが、私たちが普段接している小鹿野の方々は、本当に元気な人が多いということ。80代でもとても健康的。あくまで個人の感覚値ですが、健康寿命が都会と比べて+10歳くらい違うのではないか、という印象があります。だから会社の先輩や同僚にも「+10歳生きたくない?」って言って誘ってるんです(笑)。
命あっての人生だし、空気がいいとか、水がいいとか、体を動かす機会が多いとか、そういう環境って大きいですよね。都会の方々にとって非日常の大自然が日常になると、わざわざ休日に旅行にいかなくても、ご近所づきあいや農作業などで十分に楽しめる。ある意味、私たちが「こういう環境は健康にもいいし、本当に楽しいよ」って実証しているようなものなんじゃないでしょうか。
【関連記事】


秩父郡小鹿野町(おがのまち)では、移住を検討されている方向けに、実際の生活を体験できる「おためし移住住宅」を提供しています。リアルな暮らしを体験いただけるよう、町民とのコミュニケーションや農作業体験、鳥獣害対策見学などのアクティビティも選択できるコーディネーター伴走型、2泊~最長9泊が可能で、利用料は無料(2025年12月現在)です。移住のご検討にあたっての情報収集として、ぜひお気軽にご利用ください。