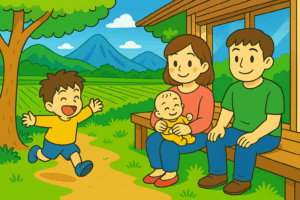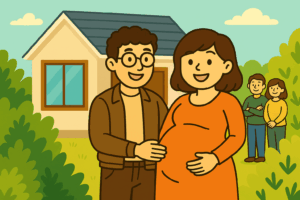「がんばー!」「いけるいける!」
6歳の息子が、初めてボルダリングの壁に挑んだ日。ジムにいた大人たちの声援が、静かな山あいの町に響いた。
埼玉県小鹿野町。この町のクライミングパークは、ただの運動施設ではない。
子どもも大人も、地元の人も移住者も、フラッと訪れた観光客も。
誰もが“自分のペース”で登り、励まし合い、つながっていく場所だ。
この場所の施設管理をするのが、東京・練馬から移住した高野さん。
林業、小売業、酒蔵、子育て、そして現在のクライミングパーク神怡舘の管理者と、多様な人生をこの町で重ねてきた。
「仕事で悩むこともあった。でも、ここに来てから“本当にやりたいこと”が少しずつ見えてきたんです」
静かだけど、確かな手応えのある暮らし。
ボルダリングをきっかけに、小鹿野町で見つけた生き方の話を聞いた。

Q. 高野さんが小鹿野町に移住したきっかけを教えてください。
ー完全に移住したのは、2010年ですね。
その3年前、佐渡島で太鼓集団「鼓童」に関わっていて、東京・練馬に戻ってからも仕事と並行して
和太鼓の演奏を続けていました。そんなとき、鼓童時代の先輩(今の妻なのですが)から
「小鹿野で演奏の仕事を手伝ってほしい」と連絡がありました。
尊敬するプレーヤーだったので、迷わず手伝いに行くようになりました。
七夕フェスや春祭り、地元のの太鼓の会にも関わるようになりました。
通ううちに小鹿野の空気や人のあたたかさに惹かれ、移住を決意。
免許も持っていなかったので、合宿で急いで取得しました。
Q. 小鹿野に住んでみて、どんな印象を持ちましたか?また、これまでどんな仕事を経験してきましたか?
ー最初に感じたのは、「ここは子育てがしやすい場所だな」ということでした。
妻には当時3歳の子どもがいて、一緒に暮らし始めたのですが、町の雰囲気がゆったりしていて、
気を張らずに過ごせたのがよかったですね。
3人での暮らしも、共働きならなんとかなるだろうと、気負わずスタートしました。
その後、小売や酒蔵などいくつか転職を経験しました。
再び林業に戻ったとき、草刈り中に手を大けがしてしまって、神経の機能が一部戻らなくなりました。
その時、クライミングや太鼓を続けられるのか、不安にもなりました。
でも改めて、「このままでいいのか?もっと自分のやりたいことをして生きていこう」と強く思ったんです。
ちょうどそのタイミングで、クライミングパークで正職員を探しているという話をもらって、今に至ります。

Q. 日々の暮らしや、子育てしていく上で小鹿野でよかったと思うことはありますか?
そうですね、暮らしの面では、やっぱり自然の近さでしょうか。
うちは薪ストーブを使っていて、子どもたちは「リアルな火」の扱いにも慣れています。
今の子どもたちって、都市部に住んでいると「火」を見たことがない子が多いんですよね。
キッチンはIHのこともあるし、タバコも吸わないからマッチも家にない。
僕らの子ども時代は、火で遊んだり、焚き火を囲んだりってことが当たり前にあったけど、
今はそういう機会が本当に少なくなったなと感じます。
一方うちの子たちは自分で薪を割ったり、火を起こしたりできる。
薪づくりも家族の共同作業です。山に木を取りに行って、持ち帰って切って、割って…。
長男は中学生で斧を振れるようになって、次男も娘も薪割りをします。
冬は火を起こせば自然と子どもたちが集まってくる、そんな暮らしが気に入っています。
長く住んでいると慣れてしまうのかもしれませんが、都市部に住んでいる人から見たらすごく贅沢な時間です
確かにそうかもしれないですね(笑)
川遊びも当たり前にできるし、山にもすぐ行ける。
川で遊んだり、岩から飛び込んだり。自然の中で体を動かすことが、日常的にできます。
僕がクライミングを再開したのも、娘がきっかけでした。
今の目標は、娘と末っ子の息子を連れて二子山に登ることなんです。
60メートルのロープで少しずつ登っていくんですが、振り返った景色が本当にすごいんです。
残酷なまでに美しいなと感じるほどです。美しすぎて、逆にちょっと怖くなるような感覚です。
「この景色を子どもたちと一緒に見たい」——それが今の一番の願いですね。
自分の住む場所がいかに美しくて、豊かで、時に少し怖いほど“本物”だということを、体で感じてほしいと思っています。
それに、小鹿野って少し騒いでも誰も文句を言わない。
東京なら怒られてるようなことも、ここでは自然の中に吸い込まれていく。
そういう自由さも、この町のいいところだなと感じています。
Q. このクライミング施設には、どんな人が来ていますか?また、大切にしていることは?
ー小学生から70代まで、初心者も経験者も幅広い人が訪れます。
地元の方だけでなく、観光で立ち寄る人や、他のジムで登っている方も「どんなところか見てみたい」と来てくれます。
課題の内容や空間の工夫も欠かせません。
去年からはベンチを置いて、自然に交流が生まれるようにしました。
コロナ禍では地元の人中心でしたが、それだけでは閉じた空気になってしまう。
だから外部のセッターを招いたり、知人の力を借りながら、少しずつ開かれた場所へと育ててきました。
最近では大会も開けるようになり、この町の中に新しい動きが確実に芽生えてきています。
課題も多いですが、ここからまた、新しいチャレンジが生まれていくといいなと思っています。

Q. 高野さんにとって、クライミングの魅力とは?
ー クライミングって、ただ登るだけじゃなくて「自分と向き合う時間」なんですよね。
力まかせでは登れないし、焦ったら余計にダメになる。
今の自分の状態を見つめて、一手ずつ確かめながら進んでいく。そういう丁寧さが必要なんです。
それに、年齢を重ねてもずっと楽しめる。若い頃は勢いで登れた場所も、今は工夫しないといけない。
だけど、だからこそ登れた時の達成感があるし、「今の自分でもまだできる」って思わせてくれる。
そして何より、人とのつながりが自然に生まれるところ。
同じ壁を登っていると、子どもも大人も関係なく「がんば!」って声が出るし、登れた時は一緒に喜べる。
クライミングって、そういう“共感”が自然と交わるスポーツだと思います。
高野さんの熱い気持ちが伝わって来るお話をたくさん伺いました。
ありがとうございました!
紹介した施設 クライミングパーク神怡館
埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2245
写真・文章 移住相談員 松田遼(Instagram)
「小鹿野での暮らしをもっと知りたい」と思った方へ。
実際に来て、町の空気や人とのつながりを体感できる移住体験ツアーをご用意しています。
👉 移住体験ツアーはこちら